PUBLICATION
No.138
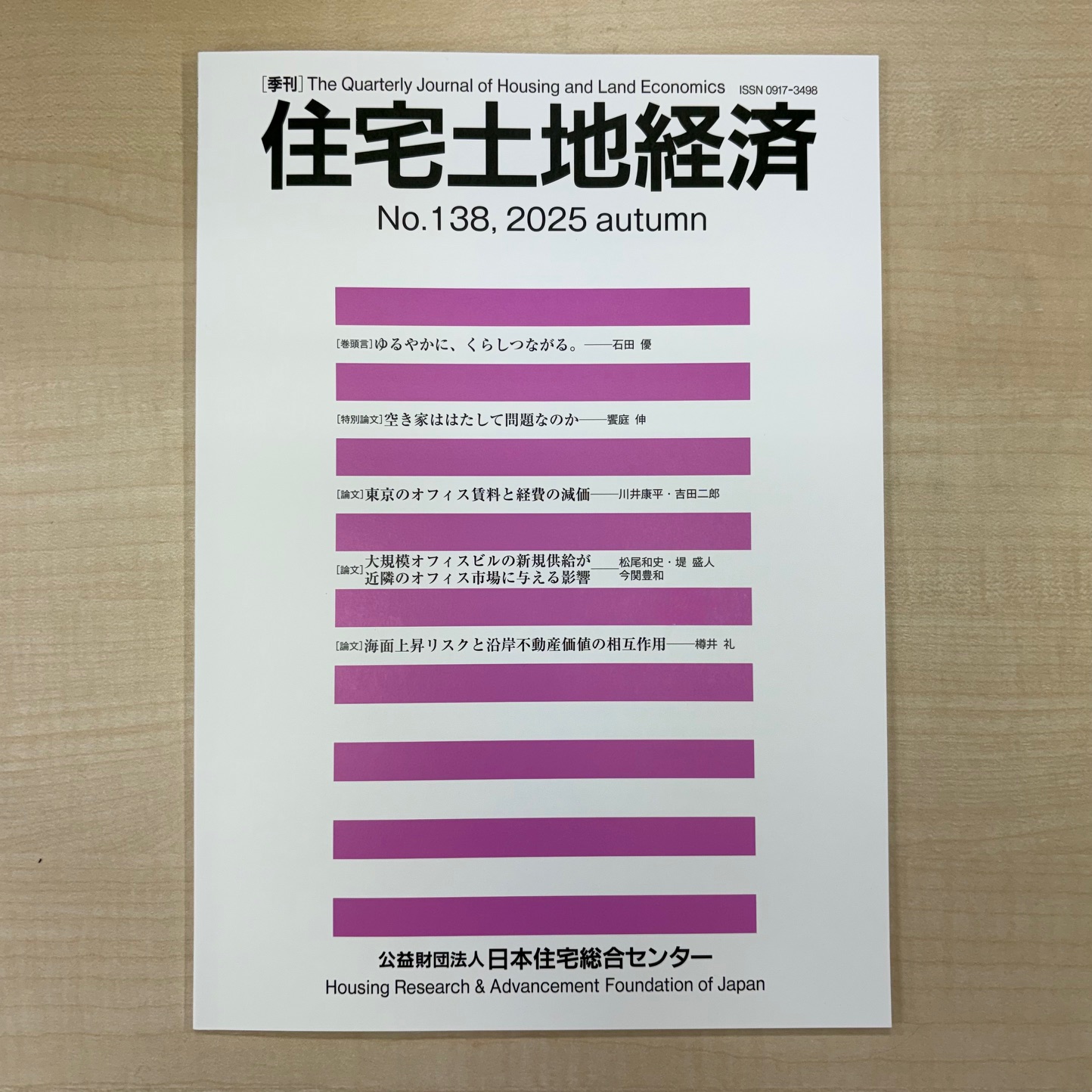
発行年月2025年10月
価格(税込) 786円
判型B5
頁数40頁
PDF 無
在庫○
目次
| 分類 | ページ | テーマ | 著者 |
|---|---|---|---|
| 巻頭言 | 1 | ゆるやかに、くらしつながる。 | 石田優 |
| 特別論文 | 2-7 | 空き家ははたして問題なのか | 饗庭伸 |
| 論文 | 10-19 | 東京のオフィス賃料と経費の減価 | 川井康平・吉田二郎 |
| 論文 | 20-27 | 大規模オフィスビルの新規供給が近隣のオフィス市場に与える影響 | 松尾和史・堤盛人・今関豊和 |
| 論文 | 28-35 | 海面上昇リスクと沿岸不動産価値の相互作用 | 樽井礼 |
| 海外論文紹介 | 36-39 | なぜ住宅の仲介が難しいのか | 増田悠人 |
エディトリアルノート
本誌でも住宅の経済的減価率を調べる論文が複数掲載されているように、不動産の経済的減価率を調べることは、大きなテーマの一つである。川井康平・吉田二郎論文(「東京のオフィス賃料と経費の減価」)は、オフィスの経済的減価率の推定方法を提案し、東京23区のオフィス・データの分析に応用している。
不動産価格の経済的減価率は、生存バイアス、建設費用増加率、機能の陳腐化などによるさまざまな影響を受ける。川井・吉田論文では、経済的減価率から機能の陳腐化の影響をどのように除くかを課題にしている。例えば、鈴木・清水(2025)は、分析したデータに含まれているマンションにおける施設情報を用いて、この課題に取り組んでいる。しかし、現在のところ、オフィスに関しては、空調設備やネットワーク施設などの詳細な施設情報が含まれたデータは存在しない。では、どのように対処すれば良いのだろうか。
被説明変数を住宅価格とした分析の際、(i)築年数、(ii)取引時点を説明変数に用いることはよくある。さらに、建設時の住宅の規制や住宅機能が反映されると考えられる年代の効果である、(iii)コホート効果と呼ばれる変数を追加することが、望ましい分析と考えられている。しかし、これら3つの変数の間には、「取引時点 - 築年数 = コホート」という線形関係があり、これらを含めると回帰式を推定できないことが知られている。このことは人口統計学で知られている問題であり、このコホート効果を考慮した分析では、線形関係に対処する方法が提案されている。
このような線形関係を含む回帰式を推定する方法として、川井・吉田論文ではIntrinsic Estimator(IE)法が使われている。分析の結果、住宅機能の陳腐化を反映するコホート効果を除くことにより経年減価率が、小さくなることが示されている。さらに経年減価を物理的劣化による部分と機能的陳腐化による部分へ分解する分析も行ない、機能的陳腐化による経年減価への影響が大きいことが示されている。
商業用不動産は、不動産投資信託の重要な投資先である。オフィスの機能を考慮すると、経済的減価が半減するという結論は、オフィスへの投資の際に、投資家に重要な示唆を与えていると考える。どのようなオフィスの機能が、経済的減価に影響するのかについて将来、より具体的かつ精緻な分析を行なうためにも、データ整備が急務であることを示していると考える。
◉
松尾和史・堤盛人・今関豊和論文(「大規模オフィスビルの新規供給が近隣のオフィス市場に与える影響」)は、新規に建設されたオフィスが近隣のオフィスに及ぼす影響を調べている。オフィスの供給は需要を取り込むため、周辺物件の賃料や価格の伸びを抑制する効果を持つ。この効果は「供給効果」と呼ばれている。一方で、新規供給は、飲食店や商業施設、公共空間等の地域アメニティの充実化を通じて、エリア価値の向上に寄与し、賃料や価格を上昇させる効果も持つ。これを「アメニティ効果」と呼んでいる。
そして、これらの効果はトレードオフの関係にあり住宅市場では、いくつかの研究がある。これらの研究を、東京の中心部で過剰供給と指摘されることもあるオフィス市場に拡張したのが本研究である。オフィスを仲介する企業の保有する2000年から2023年までの東京23区内の賃貸オフィスビルの個票データを分析した結果、地域や物件の種類により、トレードオフの関係が異なることを示しているが、新規供給が需給バランスの著しい悪化を招くものではないことを示している。
松尾・堤・今関論文の特徴は、採用された識別戦略にある。オフィス市場で新規に供給される物件は、物件価格・賃料の上昇の見込まれる土地が選ばれる選択バイアスの存在、近接地域で複数の物件の供給がされる場合には処置効果の大きさに影響が出る。このような問題を回避する必要がある。このために2つの識別戦略に基づく分析が行なわれている。分析対象地域は東京都区部であり、都心部(Central Business District: CBD)を都心5区(千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区)とし、CBD内とCBD外と分けている。
第1の分析は、CBD外を対象とし、近隣で類似した物件供給のなかった地域を対象とした差の差の分析法の適応である。供給された物件から前後4年間で半径1.5㎞以内を処置群地域とし、その外側を対照群地域としている。さらに処置群地域と対照群地域の物件の同質性を担保するために傾向スコアを求め類似した物件を選択している。第2の分析では、CBD内を対象とし、新規供給時点の差に着目した分析を行なっている。
第1の分析結果からは、新規供給の影響は新規供給から2年ほどの遅れがあり、大規模・大型ビルの募集賃料と小型ビルの募集賃料を上昇させ、アメニティ効果が強いことが示されている。第2の分析からは、大型ビルについては有意な影響が見られず、中型・小型ビルについては竣工後2年から3年後に賃料が下落傾向にあること示され、供給効果が強いことが示された。
このような結果が得られた背景についても考察されている。このなかで、ビル間の競争についても触れられている。特に、都心5区内であれば、競争は激しいはずで、競争に着目した分析もあり得るかもしれない。マンションの新規物件間の空間的競争を分析した論文として岩田ほか(2019)が参考になるかもしれない。
◉
ハワイは、透明度の高い青い海に囲まれ、年間を通じて海水浴が可能なことから、人気の高い観光地として知られている。豊かな環境を観光資源として保護し、多くの観光客を受け入れ、経済を発展させてきている。このため、ハワイの人々は、環境と経済活動に大きな影響を及ぼす地球温暖化や、海洋に関する環境問題への関心が高い。アメリカ合衆国の連邦政府は、地球温暖化防止の国際枠組みである「パリ協定」の離脱と再加入を繰り返しているが、ハワイ州は州としてこの協定に参加している。樽井礼論文(「海面上昇リスクと沿岸不動産価値の相互作用」)は、海面上昇リスクが、ハワイ州オアフ島における沿岸部の住宅価格に及ぼす影響を検討している。
分析で検討する仮説は、海面上昇リスクのある地域の住宅価格は、そのようなリスクのない地域の住宅価格よりも、低いとする仮説である。住環境に関するリスク、例えば、地震のようなリスクの場合、リスクのある地域とそうでない地域の平均住宅価格の比較では、リスクにさらされている地域の住宅価格のほうが低いことが多い。しかし、この研究で対象とするハワイでは、ホノルルのような海に面している地域は、海面上昇リスクにさらされてはいるが、「沿岸アメニティ」(例:海の眺望、ウォーター・フロント、砂浜への近さ)が存在するために、住宅需要も高い。このため平均値の比較では、海面上昇のリスクに直面している住宅販売価格は、海面上昇のリスクにさらされていない住宅販売価格よりも、高いのである。
このようなハワイ住宅市場のデータを用いて、住宅価格を、海面上昇リスクに関する変数で説明する、ヘドニック価格分析が行なわれている。分析では、「沿岸アメニティ」の住宅価格への影響を除いた後での、海面上昇の住宅価格への影響を調べることが重要になる。このため「沿岸アメニティ」について、計測可能な変数を可能な限り回帰式に含め、観測不能な変数の影響も固定効果として、回帰式に含めている。
分析の結果、海面上昇リスクは、住宅価格を低下させていることが示されている。また、沿岸アメニティに関連する変数は、住宅価格を高くするプレミアムを与えていることがわかった。
環境省の調査「東日本大震災における浄化槽の被害状況」によれば、東日本大震災では、津波被害を受けた地区の浄化槽は、津波浸水のない地域に比べ、多くの送風機の被害を受けた施設や、津波による浄化槽への土砂の浸入が認められた施設があったことが知られている。
ハワイ州のオアフ島でも浄化槽のような現地処理型排水設備(On-Site Disposal System: OSDS)のある住宅が多く、海面上昇や浸水は、汚水槽からの汚染流出につながる公衆衛生上の問題もある。このようなOSDSがある住宅の価格には、有意な負の影響があることが指摘されている。日本の沿岸地域にも同様な問題が当てはまり、本稿の分析はわが国の分析にも参考になると考える。
引用文献
岩田真一郎・隅田和人・藤澤美惠子(2019)「地理的市場占有率と不動産価格――東京都心10区からの証拠」『季刊住宅土地経済』114号、20-27頁。
鈴木雅智・清水千尋(2025)「マンション設備の陳腐化・修繕・経年減価」『季刊住宅土地経済』136号、10-19頁。